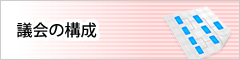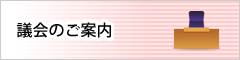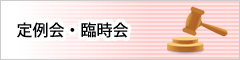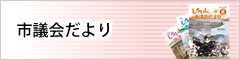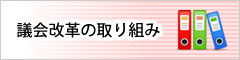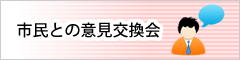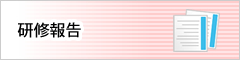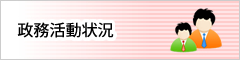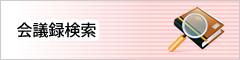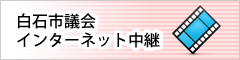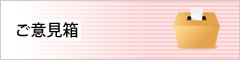議会改革特別委員会中間報告 (平成26年6月)
昨年12月に委員会を設置してから10回に渡り委員会を開催し、県内外5つの議会基本条例を参考に白石市議会の条例素案に盛り込むべき項目を検討してきました。
検討に当たっては、東京財団の必須項目としている事項や他市議会で行った「専門家との検討会記録」等を考慮に入れ、また委員以外の議員からアンケート調査を実施し、その結果を踏まえたうえで検討を行いました。

議会基本条例研修会(平成26年5月30日)
5月30日には、昨年から2度目となる中尾修さん(東京財団研究員、元北海道栗山町議会事務局長)による「議会基本条例研修会」を開催しました。
中尾研究員からは、白石市議会基本条例素案に盛り込む項目について様々なご意見をいただきました。
今回の研修会には、議会基本条例を市民と共に策定していくため、各種団体から推薦いただいた3名の市民委員にも参加していただきました。
この条例は、市民にわかりやすく、参加しやすい、開かれた議会を目指すための条例ですので、条例の策定には、市民の参加が不可欠です。
今後は、この市民委員を含めた条例策定委員会において条例案の策定を進めてまいります。
議会改革特別委員会中間報告(全文)[PDFファイル/91KB]
白石市議会基本条例素案に盛り込む主な項目について
| 条例に盛り込む主な項目 |
議会改革特別委員会中間報告(抜粋) |
東京財団 中尾修研究員からの意見等 |
| 議長、副議長の立候補制 |
- 正副議長の選出は立候補制とし、選出の経過を明確にする。
- 立候補者には、所信表明する機会を設ける。
|
- 本会議場で所信を表明することで、市民に議長選出経過が伝わる。
|
| 情報公開の徹底 |
- 市民に対して積極的に議会についての情報を発信していく。
- ホームページを活用して、本会議以外の委員会の会議録や政務活動費を公開を検討する。
- 議会映像のインターネット配信を実施する。
|
- 議会が強くなるための条例ではなく、市民にとって使い勝手の良い条例にしてほしい。
|
| 住民参加・住民との連携 |
- 市民との意見交換の場を設けることで、議員の政策立案能力を強化し、政策提案の拡大に繋げる。
|
- 多様な民意を拾えるシステムを作ってほしい。
- 住民代表機関である議会と住民が共同で行う事業とするべきだ。
|
| 市民との意見交換会の開催 |
- 全議員出席のもとに、市民との意見交換会を年1回以上開催する。
- 開催時期、内容、班編制、役割、準備、報告書の作成、市民からの意見を政策に反映させていく仕組みについては別に要領で定める。
|
- 開催方法について、開催日時や対象など柔軟に対応できるようにすることが大切だ。
- 開催の広報など、地元新聞社に協力を求めることが有効。
- 報告会直近の議会で報告することで、公式記録に残せる。
|
| 一問一答および市長等の反問権 |
- 議案の審議は、本会議を中心に行い、市民にわかりやすい議会運営を目指す。
- 本会議における議員と市長および執行機関の職員との質疑応答は、論点を明確にするため、一問一答の方式で行うことを規定する。
- 市長等による反問権は、現行の運用(質問内容の確認など)を維持するか、運用拡大(反論権)するかについて今後も研究する。
|
一問一答について
- その議会のシステムが本会議中心か委員会中心に審議を行うかを議会報告会のつど市民へ説明する必要がある。
- 委員会中心なら委員会室にもカメラを入れて公開していくべき。
|
反問権について
- 議員は質問のみに終始することから脱却すべきだ。
- 議長、委員長の議場整理権や会議規則に則って行えば、反問権(運用拡大)を入れても心配ない。
|
| 地方自治法第96条第2項の議決事項の追加 |
- 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項については、市民の福祉向上と市の発展のため拡大することを規定する。
|
- 議決事項に盛り込んで、良いか悪いかジャッジするだけではない。
- 項目を増やせばそれだけ議員の仕事は大幅に増えるので覚悟が必要だ。
- 議会は予算編成権がないから、行政計画から関与していく必要がある。
- 議案が提出されてからでは間に合わない。
ゼロベースで執行側・市民と協議できる条項を設定することが必要。
|
| 議員間自由討議 |
- 議会(本会議、委員会含む)は、自由討議を行うことができることを規定する。
- 自由討議を、議員間の合意形成を図るために用いるのか、賛否の判断材料とするために用いるのか今後も研究する。
|
- 議員同士の議論によって物事を決めていくのが議会だから、自由討議を中心とする。(自由討議に努めるではダメ)
- 初めから賛成または、反対ありきでは自由討議は難しい。
- 審議の過程で考えが固まっていくもの。
- 「合意形成」とは合議体として結果を出すプロセスを言う。(最終的に全会一致を目指すということではない。)
|
| 他の条例との関係・位置づけ(最高規範性) |
- 市議会に関する他の条例等を制定・改廃する場合は、この条例との整合を図ることを規定する。
|
- 条例の間で上下関係はないが、議会基本条例に反する条例は作らないことを明記すべき。
- 法令(国)と条例(自治体)は対等・協力の関係になることを認識すること。
|
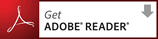 <外部リンク>
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)